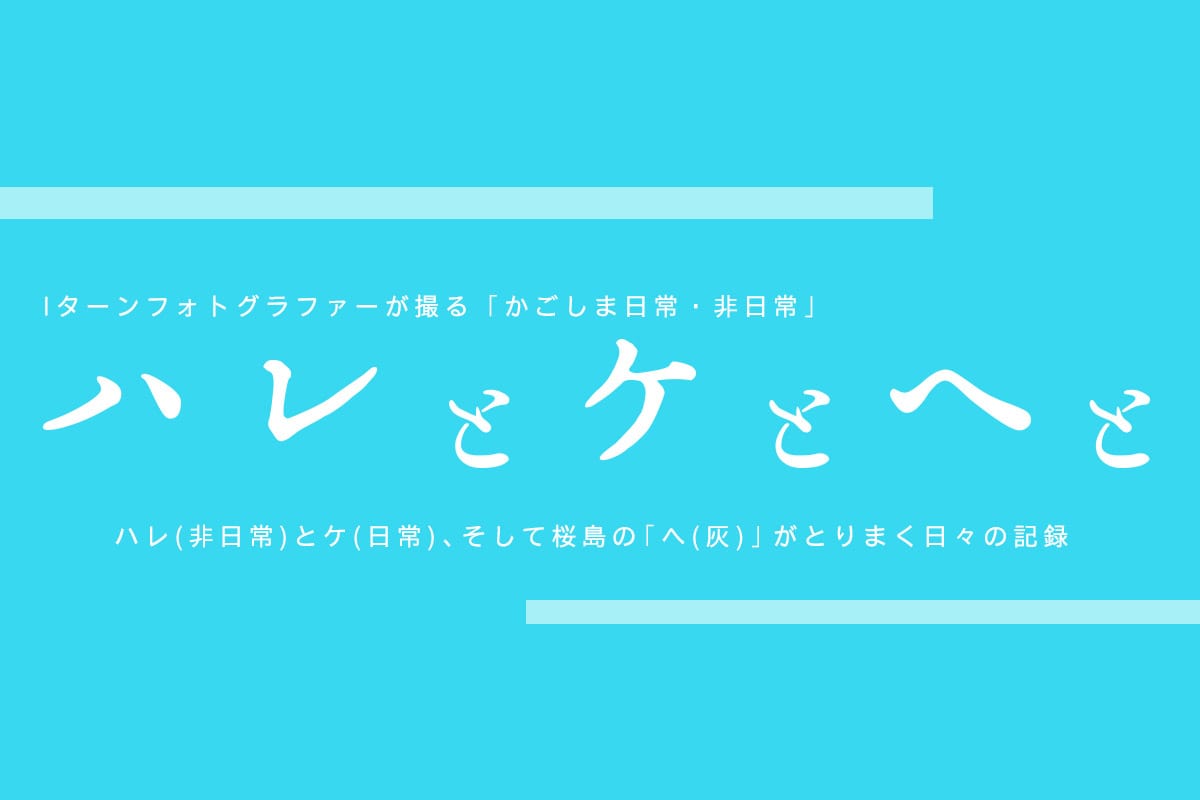縄文杉とヤクシカ
屋久島のキャンプ場に張った暗いテントの中で、僕は懐中電灯の明かりをたよりに履歴書を書いていた。写真学校の卒業を控えた、20歳の冬の終わりのことだ。しばらくはテント暮らしでも構わないから、とにかくできるだけ長く島に滞在できるように仕事を見つけなくてはならなかった。「島を撮るために、島に住む」。それは決意や覚悟を伴うような大仰なものではなく、写真を学ぶ者にとっては、ごく当たり前の選択肢(手段)のひとつだった。
屋久島をはじめて訪れたのは、18歳の夏。故郷・長崎を離れて福岡の写真学校に通っていた僕は、写真のテーマを「屋久島」に決めた。なぜ屋久島だったのか。その理由は、「とりあえず南へ。そしてなるべくお金をかけず、できるだけ遠いところへ」という程度の軽い気持ちだったように思う。
鹿児島の南に浮かぶ屋久島は、福岡からバイクで通えるちょうどいい距離だった。福岡を夕方出発し、国道3号線を片道9時間かけて南下しながら鹿児島を目指す。明け方に港のベンチで仮眠をとり、朝の8時にバイクごとフェリーに乗り込めば、お昼過ぎには屋久島の地だ。

海の向こうに屋久島の島影が浮かぶ
旅の資金はだいたい2万円が目安だった。島への交通費は往復1万2000円(ガソリン代とフェリー代)、あとは残りの8千円が尽きるまで食費や滞在費などを節約しながらテント泊で過ごす。結局、屋久島を撮り始めてから写真学校を卒業する1年半の間に(アルバイトと撮影旅行を繰り返しながら)、10回ほど屋久島へ通うことになった。

肌をジリジリと焦がす強い陽射しの中で
テントの中で書いた履歴書を受け取ってくれたのは、屋久島で情報誌を発行していた「屋久島産業文化研究所」だった。編集長の日吉眞夫氏は、静岡生まれの東京・横浜育ち。東京大学を出て広告代理店を経営していたが、昭和50年に当時廃村だった屋久島の白川山(しらこやま)へ移り住んだ。やがて詩人の山尾三省氏や多くの移住者らもムラに加わった。日吉さんは島に生きる人として、言葉と文字と深思を通して屋久島の“今”を発信し続けた人だ。
写真と文章。今の僕の仕事に関わることは、そのほとんどを日吉さんから教わった(取材のいろはから、カメラマンの本分、そしてつくり手の矜持まで)。日吉さんの下で過ごした4年を、僕は勝手に屋久島大学と呼んでいたが、長身の細い体に白い顎鬚をたくわえた姿は、先生というよりは島の仙人そのもの。両切り煙草のピースの紫煙が、いつも日吉さんのまわりをぷかぷかと漂っていた。

栗生川へダイブする島の少年
1999年、20歳の春。僕は屋久島島民になった。「最初は小さなテント生活もやむなし」と考えていたが、しばらく日吉さん宅の一室を間借りして暮らすことになった。旅人ではなく、島民として過ごす初めての夜。緊張と興奮で気持ちは高揚していたはずだが、意外にも布団にもぐりこんだ途端にスッと眠りに落ちた。夢かうつつか。深い眠りに引き込まれる一瞬のまどろみの中で聞いた、遠くの森に響くヤクシカのピィッーという甲高い声が、“やくしま暮らし”のはじまりを告げた。続く
1978年、長崎市生まれ。九州ビジュアルアーツ専門学校・写真学科卒(福岡市)。写真学校在学中より屋久島をテーマに撮影し、卒業後、移住。島の情報誌づくりに携わりながら作品制作を続け、丸4年を過ごす。25歳から鹿児島市に拠点を移しフリーランスのフォトグラファーとして活動。